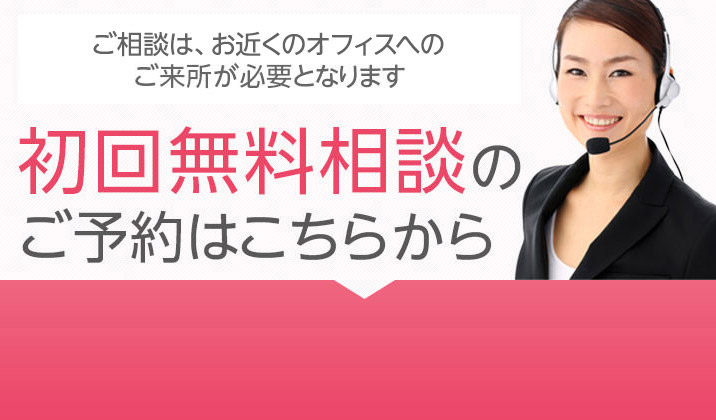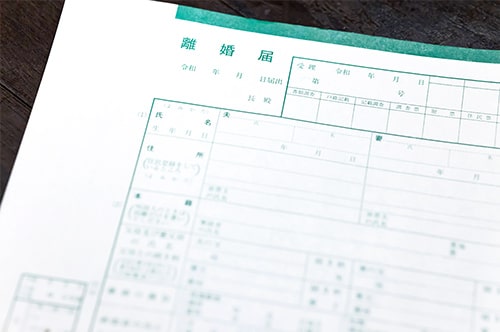配偶者に役員報酬がある場合の養育費の算定方法とは?
- 養育費
- 養育費
- 役員報酬

令和4年、八王子市に寄せられた市民専門相談は5118件で、そのうち法律相談は1591件でした。この中には離婚に関する相談も含まれるでしょう。
配偶者が会社経営者として高額の役員報酬を得ている場合、離婚に伴って支払いを受けられる養育費も高額になる可能性があります。弁護士のサポートを受けながら、適正額の養育費を請求しましょう。
本記事では、配偶者が役員報酬を得ている場合の養育費の算定方法を、ベリーベスト法律事務所 八王子オフィスの弁護士が解説します。


1、養育費の算定方法は?
養育費の金額は、離婚する父母(夫婦)の間で話し合って決めるのが原則です。話し合いがまとまらないときは、離婚調停や離婚訴訟、または離婚後の養育費の調停や審判によって決めます。
養育費の適正額は、裁判所が公表している養育費算定表を用いて計算するのが一般的です。
子どもの人数と年齢に応じた表を選択し、支払う側(=義務者)と受け取る側(=権利者)の年収が交差するポイントを確認すると、養育費の目安額が分かります。
義務者の収入が高ければ高いほど、養育費の額も高額になります。配偶者が多額の役員報酬を得ている場合は、高額の養育費を請求できる可能性が高いです。
なお、ベリーベスト法律事務所では養育費をシミュレーションできる養育費計算ツールを用意しています。ぜひご活用ください。
養育費算定表の年収上限について
なお、養育費算定表においては、義務者の年収上限が給与所得者の場合は2000万円、自営業者の場合は1567万円となっています。
義務者の年収が上記の水準を超える場合や、子どもが4人以上いる場合は、養育費算定表を利用できません。詳しい養育費の計算方法については、弁護士にご確認ください。
2、配偶者に役員報酬がある場合、養育費はどのように算定する?
配偶者が役員報酬を得ている場合は、給与収入として配偶者の収入に計上したうえで、養育費の金額を計算しましょう。
-
(1)役員報酬の金額を確認する方法
配偶者の役員報酬の金額を確認する方法としては、以下の例が挙げられます。
- 会社から配偶者に交付される源泉徴収票を確認する
- 配偶者が税務署に提出した確定申告書の給与所得欄などを確認する
配偶者が保管している書類の中に、上記の資料があるかもしれません。配偶者と同居している場合は、よく探してみましょう。
役員報酬の金額を確認できる資料が見つからない場合や、配偶者と別居していて探せない場合などには、配偶者に対して開示を求めましょう。
配偶者が開示を拒否する場合は、弁護士を通じて開示を求めることや、調停などの裁判手続きの中で開示を求めることが考えられます。 -
(2)役員報酬の額が低過ぎる場合の対処法
配偶者が会社の支配株主である場合(例:株式を100%持っている場合など)には、配偶者が自分の役員報酬を自由に決められます。
たとえば、離婚する可能性に備えて低すぎる額の役員報酬を設定するケースがあるかもしれません。また、離婚を想定していなかったとしても、節税目的などで役員報酬を低く設定するケースはよく見られます。
配偶者の役員報酬の額が低過ぎる場合は、原則どおりに養育費算定表を適用すると、もらえる養育費の額が少なくなってしまいます。
この場合は、配偶者が本来得るべき収入を計算するため、弁護士に相談の上、以下の主張などを検討しましょう。配偶者の年収として、複数年にわたる役員報酬の平均値を用いる
ずっと役員報酬が高い状態だったものの、一時的に役員報酬が低く抑えられている場合に検討すべき方法です。
会社の直近の業績が大幅に悪化しているなどの事情がなければ、平均値による役員報酬の計算は比較的認められる可能性があると考えられます。
お問い合わせください。
3、役員報酬以外に所得として計上すべきもの
会社役員の配偶者は、役員報酬以外にも別の所得を得ている可能性があります。役員報酬以外の所得も、養育費の計算に当たって配偶者の収入に計上すべきです。
確定申告書の控えなどを確認して、配偶者の収入を漏れなく把握しましょう。
役員報酬以外の所得として、よく見られるものを紹介します。
-
(1)副業の所得(事業所得、雑所得)
会社役員として活動する以外に、コンサルティングや店舗経営などの副業をしている例はよく見られます。
副業をしている場合は、事業所得または雑所得が発生している可能性が高いです。確定申告書の控えの該当欄を確認しましょう。
なお、役員報酬は給与収入である一方で、副業収入は自営収入に当たるケースも少なくありません。給与収入と自営収入が両方ある場合は、養育費の計算に当たって以下のような工夫が必要となります。- 自営収入を給与収入に換算して給与収入と足す
- 給与収入を自営収入に換算して事業収入と足す
副業が絡むケースにおける詳しい養育費の計算方法については、弁護士にご相談ください。
-
(2)不動産所得
会社役員を含む高所得者は、投資用不動産を所有しているケースもあります。
投資用不動産を賃貸して得られる収入は不動産所得に当たります。不動産所得は定期的に得られるものであるため、養育費の計算に当たっては配偶者の収入に算入すべきです。確定申告書の不動産所得欄などを確認しましょう。
なお、確定申告書に不動産所得が記載されていなくても、実は配偶者が隠れて不動産を所有しているというケースも想定されます。
配偶者が所有している不動産は、市区町村役場が保管している名寄帳の情報を確認すると分かります。名寄帳は原則として本人またはその代理人しか申請できませんが、弁護士会照会などを通じて開示を受けられることがあります。 -
(3)配当所得
配偶者が株式などの有価証券を保有している場合は、株式配当などの配当所得を得ている可能性があります。
配当所得も、不動産所得と同じく定期的に得られるものであるため養育費の計算に当たっては配偶者の収入に算入すべきです。確定申告書の配当所得欄などを確認しましょう。
ただし、上場株式などの配当所得は証券会社における源泉徴収によって課税が完了するため、確定申告がなされていないケースも多いです。
確定申告書に配当所得の記載がない場合は、配偶者が保有している証券口座に関する資料を探すか、配偶者に対して開示を求めましょう。 -
(4)利子所得
会社役員などの高所得者は、資産運用の一環として高金利通貨による外貨預金を保有していることがよくあります。
たとえば、年利5%の米ドル預金として10万ドルを預けている場合は、単純計算で1年後に5000ドル(1ドル150円なら75万円相当)の利子を得ることができます。
利子所得も定期的に得られる収入であるため、養育費の計算に当たっては配偶者の収入に算入すべきです。配偶者が外貨預金口座を持っている場合は、その口座に関する資料を探すか、配偶者に対して開示を求めましょう。
4、養育費の請求を弁護士に相談するメリット
会社役員で高所得者の配偶者に養育費を請求する際には、弁護士に相談することをおすすめします。
養育費の請求について弁護士に相談することの主なメリットは、以下のとおりです。
- 養育費の適切な金額を、法的な観点から算定してもらえる
- 相手の収入に関する資料の収集をサポートしてもらえる
- 養育費を計算する際に考慮すべき相手の収入の見落としを防げる
- 相手に養育費の減額を求められても、法的な根拠に基づいて反論できる
- 公正証書の作成や裁判手続きの対応などを代行してもらえる
- 相手と直接話す必要がなくなるので、労力やストレスが軽減される
適正額の養育費を受け取るためには、相手の収入に関する調査などをきちんと行う必要があります。調べ方が分からないときは、速やかに弁護士のアドバイスを受けましょう。
離婚事件について豊富な経験を有する弁護士のサポートを受ければ、得られる養育費の額が増え、離婚後の生活費が楽になります。養育費の請求を検討している方は、早い段階で弁護士にご相談ください。
5、まとめ
多額の役員報酬を得ている配偶者と離婚する際には、十分な額の養育費を支払うように求めましょう。
役員報酬以外にも、副業の収入、不動産収入や配当収入などを得ていることがあるので、見落とさないようにすることが大切です。
養育費の請求に当たっては、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士は、相手の収入の調査や交渉、裁判手続きなどを通じて、適正額の養育費の支払いを受けられるようにサポートを行っています。
なお、ベリーベスト法律事務所は、離婚に関するご相談を随時受け付けております。
養育費請求だけでなく、親権争いや面会交流の条件交渉などもお任せいただけます。お客さまが子どもとより良い未来を歩んでいけるように、経験豊富な弁護士が親身になってサポートいたします。
会社役員の配偶者との離婚を検討している方や、離婚協議で子どもに関する条件交渉が難航していてお困りの方は、ベリーベスト法律事務所 八王子オフィスへご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています