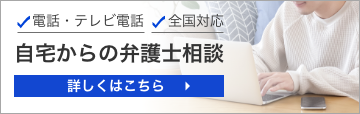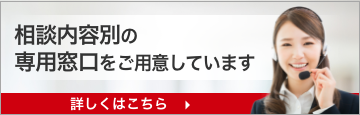就業規則を入社前に確認したいと言われたら? 対応や注意点を解説
- 労働問題
- 就業規則
- 入社前に確認

内定者から「入社前に就業規則を確認したい」と言われたらどのように対応したらよいのでしょうか。
入社前の内定者は、まだ就業していないため、対応に迷う企業の担当者も多いかもしれません。しかし、就業規則の開示義務があるかどうかは、内定者の法的な立場を正しく理解することが重要です。不適切な対応をすると、内定者との間でトラブルに発展する可能性があるため、しっかりと確認した上で対応をするようにしてください。
今回は、就業規則を入社前に確認したいと言われたときの対応とその注意点について、ベリーベスト法律事務所 八王子オフィスの弁護士が解説します。
1、就業規則を入社前に確認したいと言われたら? 拒否は可能?
内定者から就業規則を入社前に確認したいと言われたら、どのように対応するのが適切でしょうか。以下では、内定者の法的な立場と就業規則の開示義務について説明します。
-
(1)内定者の法的な立場
内定者の法的な立場は、一般的に「始期付解約権留保付き雇用契約」であると考えられています。すなわち、会社と内定者との間では、すでに労働契約が成立しているものの、労働の義務は入社日まで発生しないという状態です。法的には、内定者は労働契約が成立している「労働者」に該当するため、一般の社員と同様の法的保護を受ける権利があります。
たとえば、入社日はまだ先でも、企業と内定者との間にはすでに労働契約が成立しているため、それぞれの労働契約の解釈が適用されます。内定を取り消すことは「解雇」同様に厳格な規制が適用される可能性があります。 -
(2)内定者にも就業規則を開示する義務がある
使用者は、原則として労働基準法106条により労働者に対して就業規則を周知する義務を負っています。そのため、労働者から「就業規則を確認したい」という希望があった場合には、会社はこれを拒否することはできません。
内定者は、入社前であるもののすでに労働契約が成立しており、法律上「労働者」として扱われ、会社には、内定者に就業規則を開示する義務があります。労働契約法7条では、就業規則が周知されている場合、その内容が労働契約の一部となると規定されています。したがって、内定者にもいつでも閲覧できる状態にしておかなければ、就業規則で定める労働条件を適用できない可能性があります。
現在、在籍している従業員と同様に、内定者に対しても適切な情報提供を行うことが企業としての責任です。原則として入社後に就業規則を見せるという対応では不十分といえます。
2、内定者が就業規則を確認したい理由
内定者が就業規則を確認したいと考える理由には、さまざまなものがあります。ここでは、代表的な理由を紹介します。
-
(1)入社後にどのような環境や企業文化で働くかを知りたい
就業規則は、企業の価値や行動規範が反映されており、その会社の企業文化を知る手がかりになります。
内定者としては、これから自分が働く会社がどのような企業文化をたどってきたのか関心を持つのは当然です。入社後にどのような環境や企業文化で働くのか知りたいという思いから、就業規則を確認したいと考えることがあります。
このような内定者は、企業に興味・関心を持っていると考えられるため、入社後も活躍が期待できる人材だといえることからは、会社にとっても開示をするメリットはあると考えられます。 -
(2)内定者自身の権利や義務を確認したい
就業規則には、労働条件や職場のルールなどが記載されています。内定者は、労働条件通知書や雇用契約書により具体的な労働条件を知ることができますが、詳細については、就業規則を確認しなければわからない部分もあります。
特に入社後の昇進・昇給制度や退職に関する手続きなど、将来的に重要となる事項を把握したいと考えることも少なくありません。 -
(3)副業や休職制度など特定の制度を確認したい
会社で副業が禁止されているかどうか、休職制度が設けられているかなどは、内定者にとって重要な関心事のひとつです。これらの詳細は就職活動や面接だけでは十分に把握できないことが多いため、就業規則を確認して具体的な制度を知りたいと考えるケースがあります。すぐに副業や休職を予定しているわけではなくても、その企業で長く働きたいと考える内定者にとっては重要な事項ですので、入社前に確認したいと考える人もいます。
-
(4)他の内定を得ている企業と比較したい
内定者が複数の企業から内定を得ている場合には、各企業の労働条件や会社の福利厚生などを比較して、就職先を決めようとすることがあります。
その際、各企業の就業規則を確認し、具体的な勤務条件を比較することが重要になるため、入社前に就業規則を確認したいと考えるケースもあるでしょう。
お問い合わせください。
3、内定者に就業規則を開示する方法
内定者から就業規則を入社前に確認したいと申し出があった場合、企業は適切な方法で対応する必要があります。以下の方法を参考に、状況に応じた開示を行いましょう。
-
(1)就業規則の写しを交付する
一般的に就業規則の周知方法としては、以下の3つの方法があります。
① 事業所の見やすい場所に掲示または備え付ける
② 就業規則の写しを交付する
③ デジタルデータとして記録して共有する
しかし、内定者はまだ勤務を開始していないため、①の会社内の掲示を確認することはできません。また、外部から社内サーバーにアクセスすることも困難ですので、③のデジタルデータとして共有することも難しいでしょう。
そのため、内定者への就業規則の開示方法としては、②の就業規則の写しを交付するという方法が一般的です。内定者から就業規則を入社前に確認したいと申し出があったときは、速やかに就業規則の写しを交付する対応を検討しましょう。 -
(2)内定者が求めてきた内容を抜粋して開示する
内定者が多数いる企業では、内定者全員に就業規則の写しを開示するのは、コストや管理面で負担になる場合があります。
そのような場合は、内定者が就業規則の開示を求める理由を踏まえて、対象となる部分のみを抜粋して開示するという方法もあります。まずは内定者と協議して、そのような方法でも問題がないかどうかを確認してみましょう。 -
(3)会社のホームページに掲載する
就業規則を会社のホームページに掲載し、内定者にIDやパスワードを交付して、いつでも閲覧できる状態にするという方法もあります。
このような方法であれば就業規則の写しを印刷するコストや手間を削減でき、管理面の負担も軽減されます。特に、多数の内定者がいる企業にとっては、有効な手段となるでしょう。
4、労働問題のトラブルは弁護士に相談するメリット3つ
労働問題のトラブルを防ぎ、適切に対応するためには、弁護士への相談が有効です。弁護士に依頼することで、以下のようなメリットがあります。
-
(1)就業規則を法的な視点でチェックできる
弁護士に相談をすれば会社の就業規則を法的な視点でチェックすることができます。現在の就業規則に不備や不足がある場合には、会社の状況や法改正に応じた修正といったアドバイスを受けることができるでしょう。労働基準監督署の調査が入った際にも問題がないよう、法令に準拠した内容に整備することが重要です。
労働問題に詳しい弁護士であれば、これまでの経験や過去の判例などをもとに、企業が直面しやすいトラブルを予測し、それを防ぐための適切なアドバイスを提供します。それを踏まえて就業規則を作成・修正することで、会社の実態に合った適切な内容にすることが可能です。 -
(2)トラブルを未然に防ぐための環境を整えられる
労働者への対応に疑問や悩みがある場合は、早めに弁護士へ相談することで、適切なアドバイスを受けられます。弁護士に相談をすることで、具体的な状況を踏まえた対応策を講じ、深刻なトラブルに発展する前に問題を解決できます。
また、トラブルを未然に防ぎたいという場合には、顧問弁護士の利用がおすすめです。顧問弁護士がいれば、いつでも気軽に相談することができ、社会情勢に合わせた就業規則の修正もできるなど誤った対応をするリスクを最小限に抑えることができます。さらに、企業の実態を把握した上で、リスク回避のための環境整備をサポートすることも可能です。 -
(3)万が一トラブルになった際も対応可能
労働者との間でトラブルが生じると、その対応に時間や人員を割かなければならず、本来の業務に支障が生じる可能性があります。弁護士に依頼をすれば、労働者とのトラブル対応を弁護士に一任し、会社の負担を最小限に抑えることができます。
労働者との交渉で解決できなかったとしても、労働審判や訴訟などの対応も引き続き任せることが可能ですので、労働問題が生じたときはすぐに弁護士に相談するようにしましょう。
5、まとめ
会社から内定者に対して、内定通知を送付した時点で労働契約が成立します。実際の勤務開始はまだ先であっても、内定者は法的に「労働者」として扱われるため、企業は就業規則を適切な方法で開示する義務があります。就業規則の開示を拒否すると労働基準法違反に該当するおそれがあるため注意が必要です。
また、入社前の内定者との関係は、通常の雇用関係とは異なる特別な法的関係にあり、内定取り消しなどの対応を誤るとトラブルにつながる恐れがあります。
入社前のトラブルや就業規則について疑問点がある場合は、専門家である弁護士のサポートが重要ですので、まずはベリーベスト法律事務所 八王子オフィスまでお気軽にご相談ください。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています