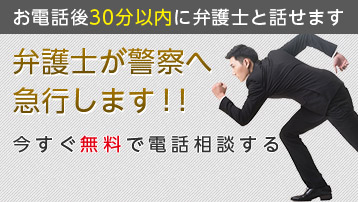検察の取り調べとは|警察との違いや取り調べを受ける際の注意点
- その他
- 検察
- 取り調べ

刑事事件で被疑者(容疑者)として捜査の対象になると、警察による取り調べが行われ、ほとんどの事件は検察に「送検」されることになります。
万が一、被疑者になってしまった場合、検察の取り調べの目的を理解しておくことは極めて重要です。
今回のコラムでは、検察の取り調べの具体的な内容や注意点、そして弁護士によるサポートの重要性について、ベリーベスト法律事務所 八王子オフィスの弁護士がわかりやすく解説していきます。


1、検察による取り調べとは
検察で取り調べを行う検察官は、刑事事件の被疑者を起訴して処罰を求めるか、不起訴処分とするか決定する権限があります。
検察による取り調べは、起訴・不起訴処分の判断や刑事裁判を見据えた重要な手続です。検察による取り調べが行われる時期や目的、その特徴について解説します。
-
(1)検察の取り調べが行われる時期
検察の取り調べは、事件が検察庁に送致(送検)された後から始まります。
被疑者(容疑者)が逮捕されている場合、警察は逮捕から48時間以内に事件を検察に送致します。
送致を受けた検察官は24時間以内に被疑者の取り調べを行い、勾留(身柄を拘束して取り調べを継続すること)の要否を判断します。
検察官が証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断した場合は、裁判所に勾留を請求して、勾留が認められると、最大20日間の身柄拘束が続くことになります。
一方、逮捕されていない場合は在宅での捜査となります。
この場合、警察での捜査期間は数週間から数か月程度行われて、送検されるのが一般的です。
送検後は、検察庁からの呼び出しに応じて取り調べを受けることになりますが、呼び出しに応じないと証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されて、逮捕されることもあるので、速やかに呼び出しに応じましょう。不安な場合は弁護士に同行を依頼することもできます。 -
(2)検察での取り調べの目的
検察官は、警察が収集した証拠や自らの取り調べを通じていくつかの重要な判断を行います。
具体的には、以下が重要な目的とされています。- 勾留の要否
- 起訴または不起訴処分の決定
- 起訴が見込まれる事件では刑事裁判での求刑内容の検討
勾留されて身柄拘束が続く場合、長期間仕事を休まざるを得なくなるなど、社会生活に深刻な影響が生じることがあります。
また、起訴されて刑事裁判で有罪となった場合は前科がつくため、起訴か不起訴かの判断は、被疑者の将来を左右する重要な分岐点となるのです。 -
(3)警察の取り調べ(捜査)との違い
警察の捜査は主に、被疑者が犯人であるか、犯罪の手口の調査、犯行動機に関する証拠収集を目的としています。一方、検察官の取り調べの目的などは、警察の取り調べと異なる点もあります。
警察と検察の取り調べの違いは以下の通りです。警察の取り調べ(捜査) 検察の取り調べ 目的 - 犯人の特定
- 犯罪の手口(手段、時期、場所など)の解明
- 証拠収集(証言、物的・状況証拠)
- 警察の証拠を総合評価
- 最終的な処分の決定
取り調べの対象 被疑者、参考人、目撃者 主に被疑者 供述調書の役割 初期の証拠資料 起訴後の裁判で重要な証拠になる
検察官は警察の集めた証拠を評価し、最終的な処分である起訴・不起訴を見据えた取り調べを行います。
-
(4)検察の取り調べの特徴
警察での取り調べは、被疑者が犯人であるという見立てで行われ、自白の獲得を重視する傾向にあるため、厳しい印象を受けることが多いでしょう。
これに対し、検察官の取り調べには以下のような特徴があります。- ① 起訴・不起訴の判断材料を集めるため、被疑者に有利な事情についても丁寧に確認する
- ② 起訴する場合に備えて、警察での取り調べ内容を再度確認される
①の例としては、被疑者の反省の態度や、示談の状況、家族のサポート体制なども重要な考慮要素となります。
②の確認の際、警察での供述内容や客観的な証拠と矛盾する弁解をした場合には、その理由について厳しく追及されることもあります。
2、検察による取り調べの流れ・回数
送検後も警察による捜査は継続しますが、検察官が必要と判断したタイミングで検察庁からの呼び出しを受け、取り調べが実施されることになります。
ここでは、検察による取り調べの流れや回数の目安について解説します。
お問い合わせください。
-
(1)取り調べの流れ
検察官の取り調べは、検察庁の執務室や取り調べ室で行われます。
逮捕されている場合は警察署の留置場から検察庁へ押送され、在宅で捜査されている場合は指定された日時に検察庁へ出頭することになります。
取り調べには、一般に検察官と検察庁の職員である検察事務官の2名が立ち会います。
検察での取り調べの流れは以下の通りです。- ① 黙秘権や弁護人選任権の説明
- ② 検察官からの事件の確認・聞き取り
- ③ 供述調書の作成
- ④ 被疑者による、調書の内容の確認
- ⑤ 被疑者による、署名・押印
なお、検察官は複数の事件を担当していることから、実際の取り調べ時間は1〜2時間程度のことが多く、待ち時間のほうが長いということもよくあるようです。
-
(2)取り調べの回数
検察での取り調べ回数に決まりはありませんが、逮捕・勾留されている場合は、以下のタイミングで3回程度実施されるのが一般的です。
1回目 送検直後 送検から24時間以内に、検察官は勾留請求か釈放かを判断する必要があるため、事件についての弁解を聴く取り調べを行います。 2回目 勾留期間中盤 警察の捜査による証拠がある程度収集された段階で、警察での取り調べ内容の確認や、検察官独自の質問事項について取り調べが行われます。 3回目 勾留期間終盤 勾留期間が終了するまでに、起訴・不起訴の判断、または処分保留での釈放を決定するための取り調べが行われます。
在宅での捜査の場合は、捜査の進捗や被害者との示談交渉の状況などに応じて、取り調べの回数やタイミングは異なります。
-
(3)警察と同じことを聞かれる理由
検察の取り調べでは、警察の取り調べで聴取された内容について、再度確認が行われることが少なくありません。
「なぜ同じ内容を何度も聞かれるのか」と疑問に思われる方もいらっしゃるでしょう。
実は、重複する内容の取り調べには重要な意味があります。検察官は、警察での取り調べ内容と同じ供述を引き出し、検察官調書として残すことを意図しているのです。
これは刑事裁判のルールが関係しています。警察や検察での取り調べにおいて、被疑者が自身に不利な事実を認め、署名・押印した供述調書は、刑事裁判で証拠として採用される可能性が高くなるのです。
もし刑事裁判となった場合、警察や検察で一貫した供述をしていると、法廷で異なる弁解をしても、裁判官の信用を得ることは困難となってしまいます。このような検察官の意図を理解した上で、取り調べに臨むことが大切です。
3、検察から取り調べを受ける際のポイント・注意点
検察で取り調べを受ける際の具体的なポイントと注意点について解説します。
-
(1)なるべく早く弁護士のサポートを受ける
検察の取り調べを受ける際には、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
理想としては、警察の取り調べを受ける段階から弁護士のアドバイスを得ることで、警察や検察の取り調べにおいて、一貫した方針で臨むことができます。 -
(2)罪を犯したことについては反省の態度を示す
検察による取り調べは、起訴・不起訴などの処分を決定することが目的のひとつです。
そのため、罪を犯したことについては真摯に反省の態度を示すことが重要です。また、今後の更生への意欲や、被害者への謝罪、被害弁償の意思があることなども、取り調べの中で説明できるよう準備しておきましょう。
特に、弁護士に示談交渉を依頼している場合は、その旨を伝えることも有効です。 -
(3)黙秘権の適切な行使
取り調べでは、答えたくない質問への回答を拒否できる「黙秘権」が保障されています。
黙秘を貫くことは容易ではありませんが、覚えていないことやわからないことについては「覚えていない」「わからない」と答えて、安易に検察官の誘導に応じないよう注意が必要です。 -
(4)調書の内容確認と訂正要求
取り調べで作成された調書に署名・押印すると、刑事裁判になった場合には基本的に証拠として裁判所に提出されると考えるべきです。
そのため、調書に供述内容が正確に記載されているかどうかをよく確認することが重要です。もし記載内容に誤りや不正確な部分があれば、訂正を求めるか、署名・押印を拒否するようにしましょう。 -
(5)違法な取り調べは直ちに弁護士に相談する
まれに、威圧的な態度や言動、長時間に及ぶ取り調べなど、違法または不適切な取り調べが行われることがあります。
このような場合には、調書への署名・押印を拒否し、直ちに弁護士に相談してください。
弁護士は検察への申し入れや、勾留に対する不服申し立ての理由とするなど、適切な対抗措置を講じることが可能です。
なお、検察での取り調べについては、録音・録画されることもあります。録音・録画は、殺人や強盗致傷など一部の重大事件で義務化されていますが、それ以外の事件でも検察の判断や弁護士の申し入れにより実施されるケースもあります。
不当な取り調べの抑止にはなりますが、有罪方向の重要な証拠にもなり得るため、より慎重な対応が必要になります。
4、検察の取り調べに対する4つの弁護活動
検察の取り調べを受けることになった際、弁護士ができる効果的な弁護活動について解説します。
-
(1)取り調べに対するサポート
取り調べに対する弁護士のサポートについては前章でも解説しましたが、不用意な供述が不利な証拠となる可能性があるため、事前に弁護士のアドバイスを受けることが重要なポイントとなります。
なお、逮捕された場合、最長で72時間は弁護士以外の人と面会をすることはできません。留置場での生活と取り調べは精神的な負担が大きいものですが、弁護士との面会は心強い支えとなるはずです。
ご家族からの依頼で弁護士が逮捕された本人と面会し、アドバイスをすることも可能です。 -
(2)示談交渉や再犯防止の環境整備
不起訴処分の獲得や刑事裁判での軽い刑の実現には、被害者との示談や再犯防止の環境整備も重要な要素となります。こうした弁護活動は取り調べと並行して進めるのがより効果的です。
しかし、捜査中に事件の関係者が被害者と接触すると、証拠隠滅と捉えられるリスクがあるので、示談交渉は弁護士に依頼するのが賢明でしょう。
再犯防止の環境整備においては、本人が「二度と犯罪を起こさない」と約束するだけではなく、ご家族による生活面の監督など、具体的な態勢を整えることが有効です。弁護士は、環境整備についてアドバイスを行い、検察官への積極的な働きかけを通じて、不起訴処分などの有利な処分を目指します。 -
(3)早期釈放に向けた活動
逮捕・勾留されてしまった場合、早期釈放の実現に向けた弁護活動も重要です。具体的には、勾留に対する不服申し立てや、再犯防止策の整備、被害者への謝罪・示談など、身柄拘束の必要性を低減させる弁護活動を取り調べと並行して行います。
-
(4)刑事裁判に向けた継続的弁護活動
起訴される見込みが高い事件では、早期の保釈や執行猶予判決を獲得するための弁護活動を継続します。
示談交渉や情状証人の手配、執行猶予を得るための環境調整など、刑事裁判に向けた準備を計画的に進めていきます。
5、まとめ
検察の取り調べは、勾留の必要性や起訴・不起訴の判断、さらには刑事裁判も見据えた重要なプロセスとなります。
検察での供述調書は、刑事裁判で証拠として採用されることを意識して作成されるため、その内容を十分に確認し、必要に応じて訂正を求めることが大切です。
取り調べに対する弁護士からのアドバイスや、取り調べと並行して行う弁護活動によって、不起訴処分や刑の軽減につながる可能性が高まります。そのため、刑事事件で捜査の対象となった場合は、できるだけ早期に弁護士への相談をおすすめします。
検察の取り調べに不安を感じている方は、まずはベリーベスト法律事務所 八王子オフィスにご相談ください。刑事弁護の経験がある弁護士が、取り調べへのアドバイスや効果的な弁護活動を行い、全力でサポートします。
- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
- |<
- 前
- 次
- >|